健康保険に加入する人
本人:被保険者
健康保険に加入している本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならないものを除く)では5人以上の従業員のいる会社や工場、銀行、商店など健康保険法で定められた事業所に働く人びとは、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
就職した人はその日に被保険者の資格を取得し、退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を失います。
また、75歳になると在職中でも健康保険の被保険者資格を失い、後期高齢者医療制度に加入することになっています。
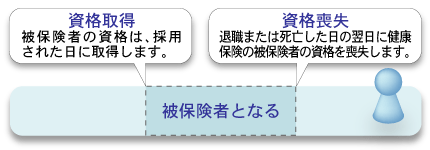
家族:被扶養者
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者となるためには、健康保険組合に申請して認定を受けなければなりません。
被扶養者申請の前に、次の事項により被扶養者に該当するかご確認ください。
(1)扶養義務者について
- ・扶養義務者は被保険者(本人)であること
- ※認定対象者について扶養義務者が2人以上いる場合には、年間収入の多い方を扶養義務者とします。
(2)被扶養者の範囲
- ・下図に示された3親等内の親族の方で、主として被保険者(本人)の収入によって生計を維持されている75歳未満の方。
被保険者と同居の内縁関係にある配偶者とその親族 - ※ 「主として生計維持されている」とは、被扶養者の生計費の半分以上を継続的に維持している状態。
(3)被扶養者(認定対象者)の収入について
- ・認定対象者に収入がある場合その額は、法律で定められた収入基準以内であり、被保険者の収入の2分の1未満であること
◆健康保険法の収入基準◆
| 認定対象者 | 年額 | 月額 | 給付金の日額 |
|---|---|---|---|
| 19歳以上23歳未満 (被保険者の配偶者は除く) |
150万円未満 | 125,000円未満 | 4,167円未満 |
| 上記以外の60歳未満 | 130万円未満 | 108,344円未満 | 3,612円未満 |
| 60歳~74歳 または障害年金受給者 |
180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
- ・年間収入とは、課税非課税を問わず、生活費に充当可能な収入すべてを含む。
※事業所得については営業収入等(総収入)すべてを収入とみなします。(ただし、一部必要経費として取扱う場合があります。) - ・失業給付、退職後の傷病手当金および出産手当金の受給者は被扶養者に加入できません。(手当日額が収入基準以下は除く)
- ・別居の場合は、仕送り金額が、認定対象者の収入額以上かつ認定対象者の年収+仕送り額(年)が年間標準生計費以上であることが必要。
その場合の証明は、受取り側の主たる口座の通帳写しをもって行います。
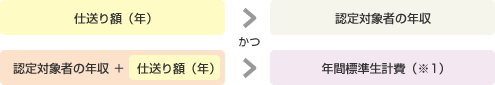
- ※1
- 「年間標準生計費」とは、人事院が総務省の家計調査等に基づき算定した標準生計費(月)を年間分に換算したもの。(標準生計費は前年に公表された金額を使用し、毎年4月に見直します)
2025年4月~2026年3月までの年間標準生計費=1人分:143万円、2人分:181万円
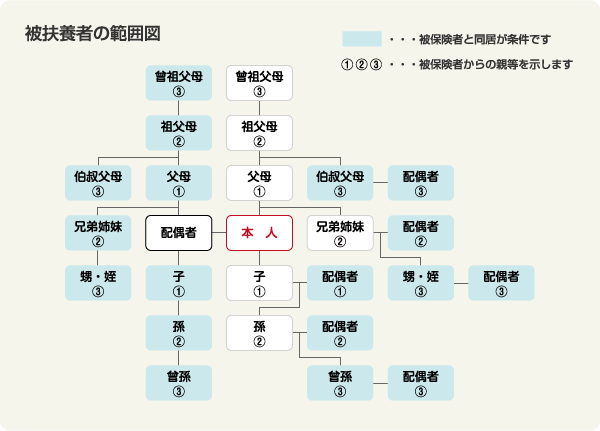
- ※同居とは・・・
住居と家計を共にする状態。
二世帯住宅や同敷地内の別の建物では、住所は一緒でも別居となります。
ただし、病院へ入院、施設へ入所、単身赴任による場合は同居とみなします。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入された場合は、すみやかに扶養減員の手続きをしてください。
- (1)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めている
- (2)労働協約・就業規則等により1週の所定労働時間が20時間以上
- (3)2ヵ月以上の雇用期間が見込まれる
- (4)月額賃金が8.8万円以上である
- (5)学生でない
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
国内居住要件
日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住居基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行するもの
- 観光、保護またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- 1~4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保護を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
被扶養者申請書類
下記提出書類のうち、住民票は個人番号の記載があるものをご提出ください。
※下記申請書類に加え、事業主へ所得税法上の規程による扶養控除親族であるか確認をさせていただきますのでご了承ください。
下表の健保所定様式の所をクリックすれば様式が表示されます。
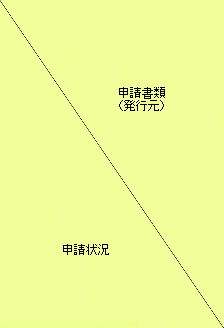 |
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
⑩ |
⑪ |
⑫ |
⑬ |
⑭ |
⑮ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳未満 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 18 歳 以 上 |
大学・各種学校・予備校生 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 勤労収入がある方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 年金収入がある方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 自営業の方 | ● | ● | ● | 廃業した場合は「廃業届」も必要→ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 無収入の方 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 退 職 し た 方 過 去 2 年 以 内 |
失 業 給 付 |
受給資格なし | ● | ● | ● | ● | ←雇用保険資格喪失確認通知書または離職票未発行証明でも可 | ● | ● | |||||||||
| 受給予定または申請中 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ※4 | ||||||||||||||||||
| 延長申請(延長中の方は過去4年以内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 受給しない | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 受給終了 | ● | ● | ● | ● | ←「支給終了」が印字されているもの | ● | ● | |||||||||||
| 雇用保険未加入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 傷病手当金、出産手当金を受給している方(予定含む) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
☆上記複数の状況にあてはまる場合(年金とパート収入等)には、該当する項目全ての証明書類が必要です。 |
||||||||||||||||||
| そ の 他 |
☆上記の書類に加え、下記の書類が必要 | |||||||||||||||||
| 障害者の方 | 身体障害者手帳(写)または療育手帳(写)←都道府県等 | |||||||||||||||||
| 外国籍の方 | 住民票(在留期間・続柄が表記されているもの)←市区町村等※7 | |||||||||||||||||
| 養子縁組をした方 | 戸籍謄(抄)本または住民票(続柄が表記されているもの)←市区町村※7 | |||||||||||||||||
| 年金収入がない方 (65歳以上) |
被保険者記録照会回答票←年金事務所 | |||||||||||||||||
| 別居の方 〔配偶者、子は除く。 ただし海外留学による場合は必要です〕 |
仕送り証明書(3ヵ月以上)←受取り側の主たる口座(光熱費等の引落しや年金等の振込がある)の通帳写し※5 | |||||||||||||||||
| 内縁関係の方 | 住民票(続柄が表記されているもの)←市区町村等※6※7 | |||||||||||||||||
- ※2
- 認定対象者の年金額が遺族年金の関係で変更があり上記④が提出できない場合、変更後の年金証書(年金額が明記)の写しでも可。
- ※3
- 認定対象者以外の所得証明書または非課税証明書を提出していただく方。但し、当健保の被扶養者である方は不要。
| 認定対象者 | 所得証明書または非課税証明書を提出していただく方(扶養義務者の確認) |
|---|---|
| 子 | 配偶者(当健保扶養家族の場合は不要) |
| 兄弟姉妹 | 父母(認定対象者と同居の場合。別居の場合は不要) |
| 孫 | 子(孫の両親) |
| 父母 | 認定対象者の配偶者 |
- ※4
- 申請中によりすでに上記⑦をハローワークへ提出された方は上記⑧で可。
- ※5
- 仕送りはボーナス時のみや数ヵ月まとめての送金ではなく、毎月定額の送金を実施していること(手渡しは不可)
- ※6
- 続柄が「未届けの妻」等が表記されているもの。(「同居人」は不可)
- ※7
- 発行後3カ月以内の世帯全員の住民票(コピー可)で、「個人番号が記載されている」もの
◎続柄、申請内容により上記以外にも書類を提出していただく場合がありますので、予めご了承ください。
☆提出ルート☆
- ・㈱ジェイテクト(本・支社、営業所、出向者)
:申請者⇒人事部人財支援室 (本社 旧本館 ジェイテクトサービス㈱ 内)⇒健保組合 - ・㈱ジェイテクト(各工場、大阪事業所、東日本支社)
:申請者⇒各工場総務担当者⇒人事部人財支援室(本社 旧本館 ジェイテクトサービス㈱ 内)
⇒健保組合 - ・上記以外のグループ企業: 申請者⇒事業所担当者⇒健保組合
- ・任意継続被保険者: 申請者⇒健保組合
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合
-
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
また、前期高齢者(65歳以上〜75歳未満)の方でも「寝たきりなど一定程度の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた方」も後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となり、健康保険組合の加入資格を失います。



